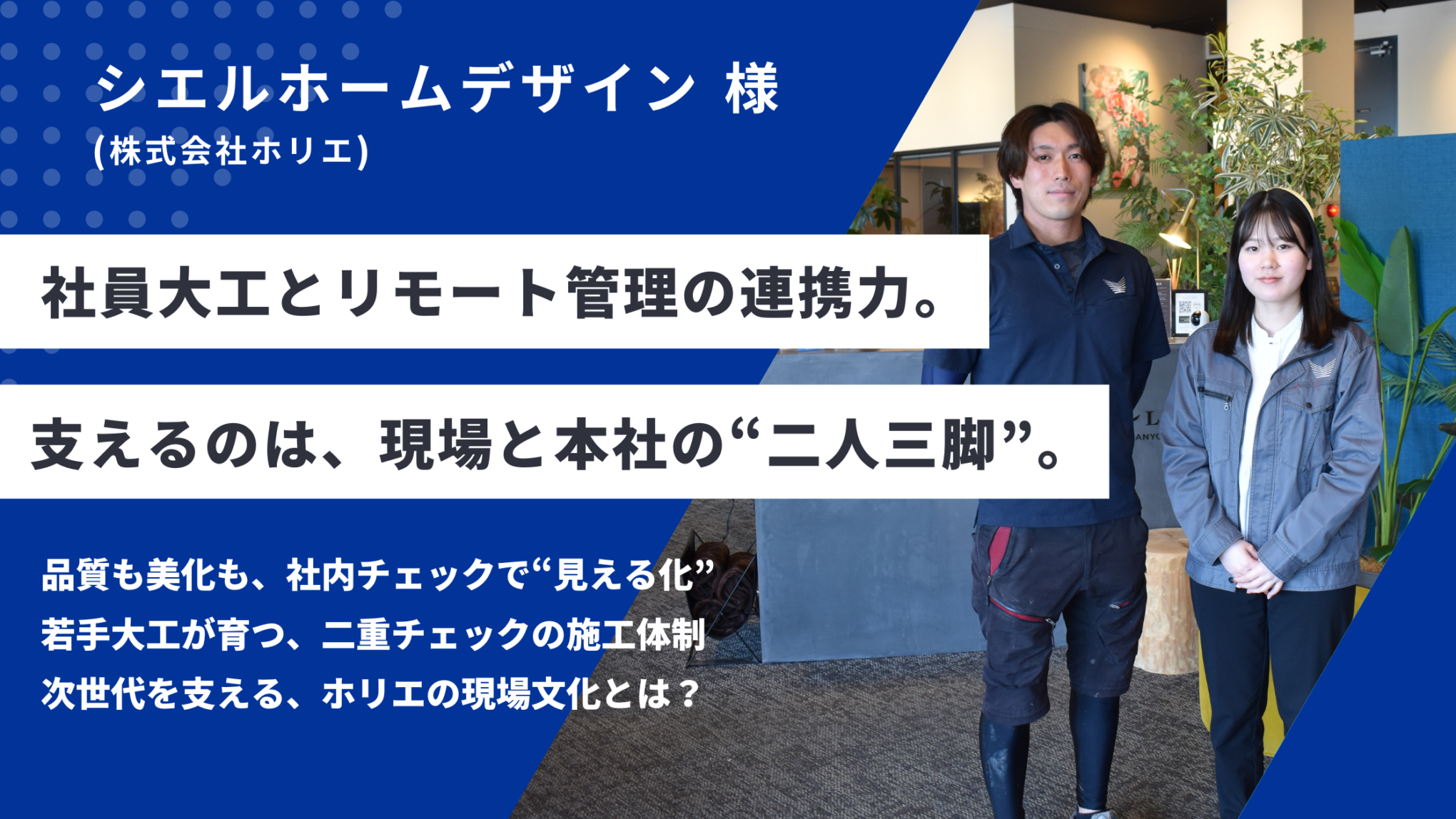
今回は、福島・山形・仙台の多拠点で年間80棟の株式会社ホリエ(シエルホームデザイン) 阿部様、高橋様へインタビューをさせていただきました。
現場監督の課題
![]() 若手の施工に“これで合ってるかな?”という小さな不安が残る場面もあった
若手の施工に“これで合ってるかな?”という小さな不安が残る場面もあった
![]() 現場美化は意識されていたが、チームや人によって捉え方に少し違いがあった
現場美化は意識されていたが、チームや人によって捉え方に少し違いがあった
![]() 品質には妥協しないものの、判断が遅れれば修正の負担が大きくなることもあった
品質には妥協しないものの、判断が遅れれば修正の負担が大きくなることもあった
現状と効果
![]() 全社統一の美化基準が根づき、“整った現場こそが信頼の証”という文化が定着した
全社統一の美化基準が根づき、“整った現場こそが信頼の証”という文化が定着した
![]() 要所ごとの段階検査が運用ルールとして確立し、“品質のバラつきを生まない施工体制”を実現した
要所ごとの段階検査が運用ルールとして確立し、“品質のバラつきを生まない施工体制”を実現した
![]() 本社から現場を支える役割が組織内に定着し、“技術と経験が循環し続ける組織”へと広がった
本社から現場を支える役割が組織内に定着し、“技術と経験が循環し続ける組織”へと広がった
ーまず初めに、会社について教えてください。
株式会社ホリエ(シエルホームデザイン)は、山形・仙台をはじめとした東北エリアに拠点を持つ、多拠点型の住宅会社です。
地域に根ざしながらも、拠点を越えて人材・技術・文化を連携させる体制を構築し、注文住宅における新たなスタンダードを打ち立てようとしています。
年間施工棟数は80棟超。2020年以降は仙台支店を開設し、福島・山形・仙台の各エリアを分担する体制へと進化。拠点ごとに特色ある取り組みを進めながらも、品質や思想を全社で統一できる理由。それは、「人を信じて任せる」文化と「技術を言語化して伝える仕組み」があるからです。
なかでも、ホリエのものづくりを支える柱が、自社大工集団「シエルクラフトマンズ」の存在。
いわゆる「社員大工」という働き方で、建築技術者を社内で育成・雇用し、設計から施工、アフター対応までを一気通貫で担います。
その大工たちは、名札をつけて現場に立ち、施工技術だけでなく“思想”まで背中で語る存在。いわば「クラフトマンとしての美学」を全員が持ち、現場に向き合っているのです。
この自社職人文化は、一般的な工務店の「下請・孫請構造」とは一線を画します。
設計者の描く世界観を、大工がその意図ごと汲み取り、現場で表現する。
気密・断熱といった目に見えない性能面も、「自分の名前で建てる」という誇りを持って施工する。
その姿勢こそが、ホリエの建築品質を支えているのです。
また、ホリエの育成文化には「若手に任せる勇気」があります。
10代・20代の大工が、先輩の背中を見ながら実践で学び、2年目から後輩を指導することも日常的。
「まだ若いから」ではなく、「やってみろ」と背中を押す。それが、ホリエの原動力です。
このような“クラフトマンシップ”と“育成文化”を同時に持つ企業は、建設業界のなかでも極めて稀有な存在です。
そして今、この文化をさらに広げる力となっているのが、現場のDXを推進するLogSystemの導入でした──。
ー普段の業務について教えてください。

○阿部紘奈さん(品質管理)
私はいま、リモートで現場を支える品質管理の業務を担当しています。
大学では建築を学び、設計を志してホリエに新卒で入社しました。最初は営業を経験し、LogSystemの導入をきっかけに、工事管理部へとジョブローテーションしました。今は事務所から「LogWalk」や「LogMeet」を使って、遠隔で現場を見守る日々です。
現場の360度画像を確認し、工事の進捗や安全面、美化状況などを多角的にチェック。
大工さんや協力業者の方とも頻繁にやり取りをし、必要があれば写真を撮って監督に相談したり、改善点を伝えたりもします。
自分で判断しきれないこともありますが、それでも「現場に関われている」という実感があります。
現場に出ていた時以上に、全体の流れを俯瞰できる立場になって、知識が整理されていく感覚が面白いんです。
もともと「お家づくり」に関わりたくてこの業界に入ったので、こうして今、建築士としての学びが現場の中で活きているのは嬉しいです。
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
高校卒業後にホリエに入社して、今年で12年目です。
私は今、社員大工として施工に携わりながら、課長として山形エリア全体の統括も担当しています。仙台には部長がいて、私は山形の現場を管理する役割です。
ホリエの大工は、毎年新卒が入ってくるので、現場の平均年齢がとても若い。
私自身、20代で課長職を任せてもらい、年上の後輩を指導することもあります。
でも、この会社には「推薦してくれる文化」があるんです。僕の課長昇格も、部内の12人からの推薦と、部長の後押しがあって実現しました。
施工現場では、日々の作業に加えて、品質や安全の確保、施主との対応など、幅広く関わります。
後輩育成にも力を入れていて、今は「施工マニュアル動画」の制作にも取り組んでいます。
どうしたら若手に伝わるか、どうすればスムーズに現場を回せるか。試行錯誤しながら、伝え方にも磨きをかけています。
現場を任せてもらう責任と、後輩を育てるやりがい。
どちらも大変だけど、それ以上に「信じて任せてもらえる」ことが、誇りになっています。
ーLog Systemの導入のきっかけは、どういった事でしょうか?
○阿部紘奈さん(品質管理)
LogSystemの導入は、私が工事管理部に異動したちょうどそのタイミングでした。
会社全体として「現場数が増え、エリアも拡大していく中で、限られた人員でも安定した品質を確保するにはどうすればよいか」という課題意識がありました。
山形だけでなく、福島・仙台にも現場が広がっていくなかで、「監督がすべてを見に行く」やり方では限界がある。
その中で、“現場を見に行かなくても、確かな品質管理ができる仕組み”としてLogSystemに注目し、導入が決まりました。
特に私のように建築士の資格は持っていても、現場経験は浅かった人間にとって、LogSystemは「現場を知る」絶好の学習環境でもありました。
遠隔でも施工の良し悪しが判断できるようになるには、現場知識と構造理解が必要です。だからこそ、毎日のチェックを通じて、知識が少しずつ積み上がっていく感覚がありました。
また、「遠隔であっても、誰が見ても同じ基準で管理できる」ことで、属人性を排除し、現場のばらつきを減らせる。
これは会社としても、品質の均一化を実現するうえで大きな一歩だったと思います。
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
大工側からしても、「LogSystemがあることで助かること」は本当に多いんです。
たとえば気密や断熱の施工って、細かい部分に職人の力量が出やすい。でもLogWalkで記録が残るから、「見られている意識」も働くし、改善のきっかけにもなる。
以前は、いい施工をしていても、それを誰かに伝えたり共有する場面が少なかったんです。
でも今は「この納まり、いいね」「この断熱の収め方、真似しようか」といった会話が自然と現場で生まれるようになった。
LogWalkで現場の記録が可視化されることで、技術が“共有財産”になる。これが一番の価値かもしれません。
あとは単純に、「誰が見ても同じ基準で評価される」って、大工にとっては嬉しいことなんです。
ベテランだろうと若手だろうと、ちゃんとやっているかどうかは映像が証明してくれる。だからこそ、技術力や意識がそのまま反映されるんですよね。
ーLog Systemによって変わったことを教えてください。
品質管理の変化と“大工としての誇り”
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
LogSystemがあることで、施工の質そのものが底上げされた実感があります。
僕が現場で特にありがたいと感じているのが、「チェックしてもらって嬉しいベスト3」です。
1つ目は、壁断熱検査。
気密の処理は見えなくなる部分だし、ほんの少しの隙間や納まりで結果が変わってくる。
自分でも細かく意識してやってるけど、LogWalkで阿部さんがしっかり確認してくれてると思うと、やっぱり背筋が伸びます。
疑問があればその場で工務に相談してもらえるし、すごく安心なんです。
2つ目は、サッシ検査(開口+納品)。
これ、本当に重要で。
窓が左右逆に入ったり、高さが間違っていたりすると、外壁を貼った後に発覚して大きなロスになる。
でも、サッシが入った段階でのリモートチェックが入ることで、早期発見・早期修正ができる。
前は完成間際に気づくこともありましたが、今はミスが表に出る前に止められるんです。
3つ目は、ボード検査。
木工事の最後、天井や壁のボード貼りが終わったタイミングです。
この検査が入ることで、「これで全部やり切った!」という達成感と、阿部さんからの確認が重なって、大工としてすごく誇らしい気持ちになります。
現場の最後まで、しっかり見届けられているという感覚。これは、LogSystemがあってこその信頼関係です。

美化・安全に対する“意識改革”
○阿部紘奈さん(品質管理)
現場の美化も、LogSystemで大きく変わったところです。最初は「撮影されるから片付ける」だったかもしれませんが、今では「綺麗な現場が当たり前」という感覚に変わってきています。
月1回、エリアごとに分かれてLogMeetでパトロールもしています。
現場には社員監督と協力会の役員が立ち会い、私は画面越しにチェック。
報告内容はPDFや動画で全員に共有し、全拠点の現場で同じ基準を持てるようになっています。
○高橋侑弥さん
現場に誰かが“見に来る”ってだけで、意識がまるで違います。
撮影日が決まっているから、「その前にちゃんと片付けよう」という流れが自然にできている。
これが1回限りじゃなくて、毎回続いていくから、習慣になるんですよね。
前は、誰がどの現場をどう見るか、バラバラでした。
でも今は、誰が見ても「綺麗な現場だね」って言ってもらえる。
それが、やりがいにもなっていますし、自分のチームの誇りにもなっています。
ー品質管理の具体エピソードはありますか?
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
LogSystemの良さって、“気づき”の積み重ねだと思っていて。
リモートでのチェックがあることで、自分の施工が第三者の目に触れる。
それが日常になることで、大工としての感覚が磨かれていくんです。
たとえば、壁断熱のチェック。
ここは断熱材の納まり、気密処理、柱周りの空間の詰め方など、かなり繊細な作業が求められる場所です。
やってる本人としては「大丈夫だろう」と思っていても、阿部さんがLogWalkで「ここ、もう少し詳しく写真を撮っておきますね」と反応してくれる。
その一言で「あ、そこ注意するべきだったな」って、素直に振り返ることができるんですよ。
しかも阿部さんは、絶対に答えを決めつけない。
「どうすればいいですか?」と聞かれても、現場に立っているわけじゃないからと、判断は監督に委ねる。
このスタンスが、僕ら大工にとってはありがたいんです。
誰かに頼りすぎることもなく、自分の判断軸も育つ。
でも同時に、“ちゃんと見てくれている人がいる”という安心感がある。
さらに言えば、サッシ検査。
ここは窓のサイズや設置位置がズレると、手戻りのコストが大きくなってしまう。
LogWalkで開口チェックができることで、設置前後の確認ができ、現場の緊張感も上がります。
過去には、サッシをつけた後に「左右逆だった」と気づいたこともあります。
でも今は、阿部さんのチェックが早い段階で入るので、最小限のミスで済んでいる。
「やばいかも」と思った瞬間に、すぐ誰かとつながれるって、心強いですよ。
そして、ボード検査。
木工事の最終工程で、壁や天井の石膏ボードを貼り終える瞬間って、大工にとっては「一区切り」の場面。
そのときに、阿部さんがLogWalkでしっかりチェックしてくれると、「やりきったな」って気持ちになれるんです。
単なる“確認作業”じゃない。そこにはちゃんと、人の想いが通っているんですよね。
ー現場美化や安全についての変化はありますか?
○阿部紘奈さん(品質管理)
LogWalkによる現場チェックを始めてから、現場の「当たり前」が大きく変わってきたと感じています。
以前は、監督が月に1回すべての現場をまわって確認していましたが、今はそれが難しい。
拠点が山形、仙台、福島と増え、物理的にカバーしきれない中で、LogSystemは“分身”のような存在になってくれました。
私がLogWalkで安全パトロールをする日は、事前に撮影日が決まっているんです。
そうすると、自然と「その前に片付けておこう」と現場にいる皆さんが意識してくれるようになって。
結果として、「綺麗な現場」がどんどん当たり前になってきました。
以前は、社員大工と外部大工の間でも、現場の美化に差が出ていたんです。
でも、今では検査の基準が共通になり、LogWalkの記録をもとに全員が同じ目線でチェックされるようになった。
月1回、現場の担当者と協力会社の方が現地にいて、私がLogMeetでつないで遠隔から安全パトロールを実施。
山形・仙台チームと福島チームに分かれ、報告内容は施工管理アプリで全社共有しています。
こういう取り組みが重なった結果、「美化=評価につながる」文化が根付いてきたと感じます。
LogSystemは、単なる管理ツールではなく、現場に“いい緊張感”を生んでいると思います。
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
「見る人がいる」ってだけで、現場は変わるんです。
LogWalkで撮影して、その映像を阿部さんが見る。
「お、今日はちゃんと片付けてあるな」なんて思われるかもしれないと思うと、自然と整理整頓に気が向く。
コードが床に散らばっていたり、工具が置きっぱなしだったり、ちょっとしたことでも“見える化”されると意識が変わるんですよ。
業者説明会でLogWalkの映像を流すと、「ここ、もっと綺麗にできるよね」といった会話が自然に出てくるんです。
それって、単なる注意ではなく、職人同士の“自発的な意識共有”なんです。
今では、「コードが床に落ちていないか?」みたいな項目がチェックリストに追加されるようにもなりました。
僕自身、年上の職人さんに注意しなきゃいけない立場ですが、「LogWalkの撮影あるんで、片付けお願いします」と言いやすくなったのも大きい。
何度言っても変わらないときは、「お客様も見るので」「会社も確認しています」と伝えることで、共通認識が生まれるんです。
綺麗な現場、安全な作業、それが職人の誇りにつながる。
LogSystemは、その背中を静かに押してくれる存在ですね。
ー働き方の面での変化はありましたか?

○阿部紘奈さん(品質管理)
私は工事管理部に異動するまでは、営業として、お客様サポートのために現場に出たり、営業サポートをしたりと、日々動き回っていました。
その頃は、天候や移動距離に左右されることが多く、正直、体力的にも大変でした。
でも、LogSystemが導入されたことで、働き方は大きく変わったと思います。
今は、事務所で品質管理を行うポジションに就き、落ち着いて仕事に向き合えるようになりました。
天気に左右されることもないし、遠方の現場にもすぐアクセスできる。
「現場にいないと分からない」という固定観念がなくなって、むしろ“全体を俯瞰する目”を養うことができました。
特に女性として、今後ライフステージが変わっても、この仕事を続けられると思えることがとても大きいです。
産休や育休を経て、復職後に「リモートで現場品質を守る仕事」ができる。
それって、建築業界においては、なかなか画期的な環境だと思うんです。
「現場=男性の世界」という価値観を変えられる働き方だと思いますし、
自分のように設計を学んだけれど施工から離れていた人にも、“現場とつながる手段”を提供してくれるのが、LogSystemなんです。
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
現場サイドとしても、LogSystemがあることで感じる安心感はとても大きいです。
施工の判断に迷うというより、「自分では大丈夫だと思っているけど、本社の目でも確認してほしい」という場面はよくあります。
たとえば、断熱やサッシの納まりなど、品質に直結する多くの施工タイミングでは、
阿部さんによる「LogMeet」での15分立ち会いが行われる体制になっています。
また、360度のVRを使って現場をクラウド共有し、その上で、担当監督や阿部さん、設計部門などがしっかりチェックしてくれる。
この“二重チェックが当たり前”の環境があることで、現場としても自信を持って次の工程に進めるんです。
若手の大工たちも、「これは自分でOK出せるけど、最終確認もらえると安心だよね」と、
自然とその流れを受け入れていますし、むしろ「きちんと見てもらっている」という安心感が施工への丁寧さや責任感につながっていると感じています。
ホリエは「挑戦を後押しする文化」がある会社ですが、LogSystemは、それをしっかり支えてくれる“仕組みの土台”なんです。
ただ見てもらえる、ではなく、「任せられているけど、きちんと見届けてもらえる」。
それが、今の僕たちが自信を持って施工に向き合えている理由だと思います。
ーホリエの「育てる現場」について教えてください。
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
ホリエには毎年、新卒の大工が入社してきます。年齢構成はとても若く、現場にもフレッシュな空気が流れている。
僕自身も20代で、すでに課長という立場を任せてもらっています。
それが特別というわけではなくて、ホリエでは「若手にどんどん任せる文化」がしっかりあるんです。
実際、2年目で後輩の指導を始める人も珍しくありません。
現場で自分が教えられたことを、次の子にまた伝えていく。
“育てる側になることで育つ”という考え方が根づいていると思います。
うちの現場は「とにかくやってみろ」の文化。
大河原部長や、自分の師匠のようなベテランが、いつも背中で教えてくれる。
「まず動け、やってみろ、失敗してもいい。誰かがちゃんとフォローする」
そうやって、失敗も糧にしながら成長するんです。
教育の仕組みも進化しています。
今は「施工マニュアル動画」を作っていて、図面だけじゃ伝わらない“現場の段取り”や“納まりのコツ”を映像で共有できるようにしています。
若手が現場に入ったとき、「これがあると心強い」という声も増えてきました。
それから、ホリエには「協力会の8訓」という思想共有の仕組みもあります。
これは業者さんとも共通認識を持つためのもので、「報連相を欠かさない」「安全第一」「最後までやりきる」など、
現場で働く人が皆、同じ土台に立てるようになっているんです。
職人が職人を育てる。その輪が、今しっかり広がってきていると感じます。
ー大工としての誇りとは?(ホリエ文化)

○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
ホリエの一番の魅力は、「大工が社員として誇りを持って働ける環境がある」ということです。
多くのハウスメーカーでは、大工は外注。仕事は発注されるもの、という扱いかもしれませんが、ホリエでは違う。
僕らは“社員大工”という立場で、一棟一棟に責任を持って、品質のすべてに向き合っています。
「ただ数をこなすだけのアスリート大工にはなるな」と言われて育ちました。
棟数をこなすのがすごい、という時代もあったかもしれません。でも、ホリエでは“精度”が何よりも大切。
1棟ごとに魂を込める。建築の思想まで形にする。それが求められているんです。
実際に、社内では気密性能を示す「C値」の計測も行っています。
数値は一種の通信簿のようなもの。C値0.2や0.1を叩き出す仲間もいて、
みんなでその結果を共有して、自然と競い合っている。
自分たちの仕事の成果が、こうして“見える化”されることは、誇りにもつながります。
そして、何より「シエルクラフトマンズ」という大工ブランドがある。
名札をつけて現場に立つことの意味。
“この現場は自分が最後まで責任を持って仕上げる”という想い。
その積み重ねが、クラフトマンとしての信頼を築いていると思います。
うちでは、技術を継承することも大切にしています。
若手にどんどん任せる。時には棟梁も託す。
先輩職人が見守りながら、若い職人が自信を持って前に出られるようにする。
“任せて、育てて、支える”――そんな風土があるから、チャレンジが当たり前になる。
気密や断熱、複雑な納まり――設計の意図をどう現場で実現するか。
それは僕ら大工の腕の見せ所です。
美しさと性能、その両方を求められる今の住宅で、自分の技術を磨ける。
この環境は、本当にやりがいがあります。
安全管理や整理整頓も、クラフトマンとしての重要な責務。
現場がきれいで安全であることは、技術と同じくらい大切です。
見る人が見ればわかる。誇れる現場は、空気まで違います。
だから僕は、ホリエの大工であることを誇りに思っています。
この場所で、大工という仕事の価値を高めていけることが、何よりのやりがいです。
ーLog Systemを勧めたいのは、どんな人ですか?

○阿部紘奈さん(品質管理)
私は「建築士資格を持っているけれど、現場経験に不安がある方」にこそ、LogSystemを勧めたいです。
かつての自分がそうでした。設計の勉強をして資格も取ったけれど、
いざ現場に出ると分からないことばかりで、自信が持てなかった。
でも、LogWalkやLogMeetで現場を見るようになってからは、
「図面と現場がつながった」という感覚を持てるようになったんです。
同じ検査を何度も繰り返すうちに、「ここがポイントなんだな」と自然と理解できるようになる。
いわば“チェックして覚える”という、建築業界にはなかった新しい学び方。
それに、移動も不要で、天気にも左右されない。
ライフステージが変わっても、施工に関わり続けられる仕事って、すごく貴重だと思います。
○高橋侑弥さん(社員大工/課長)
僕は、「現場には立てないけど建築に関わりたい人」におすすめしたいです。
たとえば、身体を痛めた職人さん、出産や育児で現場から離れた方、
あるいは業界経験があっても、物理的に現場に行けない人たち。
LogSystemがあれば、現場にいなくても、その経験を“伝える力”に変えることができる。
後輩を遠隔で見守ったり、アドバイスを送ったり、知識を残す側に回れる。
これは職人にとって、キャリアの“セカンドステージ”にもなると思っています。
あとは、学校教育にも広げていきたいです。
工業高校や建築系の学生たちが、現場に入る前にLogWalkで施工を学ぶ。
そうすれば、「働く前に現場を知る」という体験ができますし、
“リモートで現場を支える”という発想が、もっと当たり前になっていくと思います。
建設業の可能性を、もっと広げたい。
そのために、LogSystemはすごく価値のあるツールだと思っています。
ー阿部様の業務の様子

シエルホームデザインは高い住宅性能が可能にする、心から快適な住み心地を重要視しています。
シエルホームデザインだからこそできる本物の注文住宅。一級建築士と自社大工職人とが在籍する工務店だからこその高品質・高性能な家づくり。


 0466-90-3381
0466-90-3381